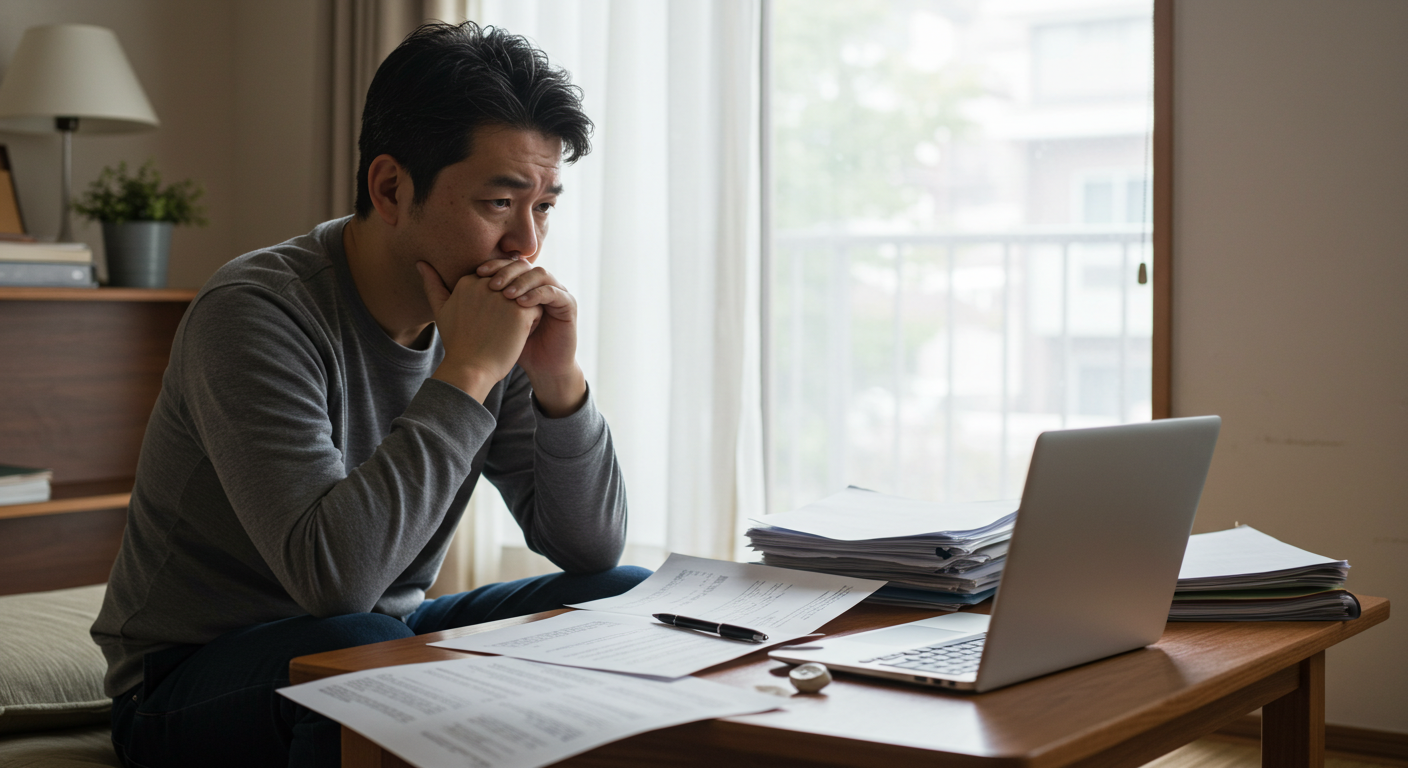「母の介護のために仕事を辞めたんです」
そう伝えると、たいてい「すごいね」「大変だったね」と言ってもらえる。
でも、実際のところは“すごさ”や“えらさ”よりも、不安とか、制度のややこしさとか、「誰も教えてくれないこと」の連続だった。
この記事では、母のくも膜下出血による入院をきっかけに、
退職・失業保険・転職活動・制度の手続きなど、僕がぶつかった“制度のリアル”を記録していきます。
母が倒れた日、すべてが動き出した
2025年1月某日。それは突然で、病名は「くも膜下出血」。
すぐに緊急搬送、手術、ICU。
あまりに急すぎて、頭の中では「仕事どうしよう?」なんて考える余裕もなかった。
手術が無事に終わったあとも、しばらく入院。
そこからは病院の送り迎え、着替えの準備、主治医との面談、
それに加えて「どこの病院に転院させるか?」という調整……。
気づけば毎日が病院中心になっていて、そのまま休職、そして退職を決意するまで、そう時間はかからなかった。
退職前にやっておいたこと
僕は会社に介護休業の申請をしたあと、有休や欠勤も使いながら限界まで粘った。
でも、母の記憶障害のリハビリが必要になり、在宅での見守りがしばらく必要になるとわかった時点で「もう限界だ」と悟った。
退職を決めたあと、やったことはこんな感じ:
- 会社の上司に介護が理由であることを正直に伝える
- 社会保険と年金の切り替え方法を調べる
- ハローワークで失業保険の申請条件を確認
- 母の介護認定やケアマネジャーとの面談に同席
どれも、「調べながら」「誰かに聞きながら」じゃないと無理だった。
制度って、どうしてこんなにややこしいんだろうって、何度も思った。
ハローワークでの違和感:「その理由じゃ認定されないかも」
退職後、最初に行ったのがハローワーク。
「失業保険(雇用保険)を受給するための申請」だ。
でも、ここで壁にぶつかる。
僕は“特定理由離職者”として認定されるつもりでいた。
家族の介護という、正当な理由があるはずだと。
でも、窓口で返ってきた言葉はこうだった。
「退職時点で、要介護の認定が出ていないと難しいかもしれません」
え?そうなの?
結局、申立書を提出し、主治医からの診断書も添えてなんとか認定は受けられたけど、
「制度を知らなかったら、損してたな」と思った瞬間だった。
特定理由離職者の制度は“知ってるかどうか”がすべて
ちなみに「特定理由離職者」に認定されると、以下のようなメリットがある。
- 7日間の待期期間だけで失業保険の給付が始まる(通常は3ヶ月の給付制限あり)
- 雇用保険の受給期間が手厚くなる場合がある
ただし、これは「自己都合退職」でも“やむを得ない事情”と認められた場合のみ。
今回のように、退職時点で「親の介護が必要だったか」「証明があるか」が問われる。
要するに、「退職してから申請すればなんとかなる」は通用しない。
転職活動、でも「介護してました」が言いづらい
退職してから数週間後、転職サイトに登録して活動を始めた。
でも、ここでもモヤモヤは続いた。
面接官:「前職を辞めた理由は?」
うまく言えない。
「介護で辞めました」と言うと、“再就職してもまた辞めそう”って思われるかもしれない。
だから、あえて「家庭の都合で」や「一身上の都合で」って濁すこともあった。
でも、それって正直に話してないわけで、ずっと罪悪感が残った。
制度のすき間に置き去りにされた気持ち
親のサポートが必要な人なんて、たくさんいると思う。
でも、その実態って、「介護認定が出たかどうか」だけじゃ語れない。
- リハビリ中の見守り
- 記憶障害のある人との暮らし
- 付き添いや話し相手の時間の消耗
こういった“見えない介助”は、制度のどこにも当てはまらないことが多い。
だからこそ、「手続きのすき間」で苦しんでる人は、僕だけじゃないと思う。
おわりに:これを読んでいる“あの時の僕”へ
もし、この記事を誰かが検索で見つけてくれているなら、
きっとあなたも、「どうしたらいいのかわからない」「制度に置いていかれてる気がする」「もう限界かもしれない」って、
今まさにどこかで立ち止まっているのかもしれません。
僕もそうでした。
ひとつひとつの手続きが重くて、
正しい選択が何かもわからないまま、
ただ“やらなきゃ”という思いだけで動いていた日々。
でも、それでもいいんです。
迷いながらでいい。
不安なままでいい。
制度は完璧じゃないけど、“自分の今”を大切にした決断は、ちゃんと未来につながります。
この記事が、あなたにとっての「道しるべ」のひとつになりますように。
そしていつか、少し心に余裕ができたら、
“あの時の自分”を誇ってあげてください。