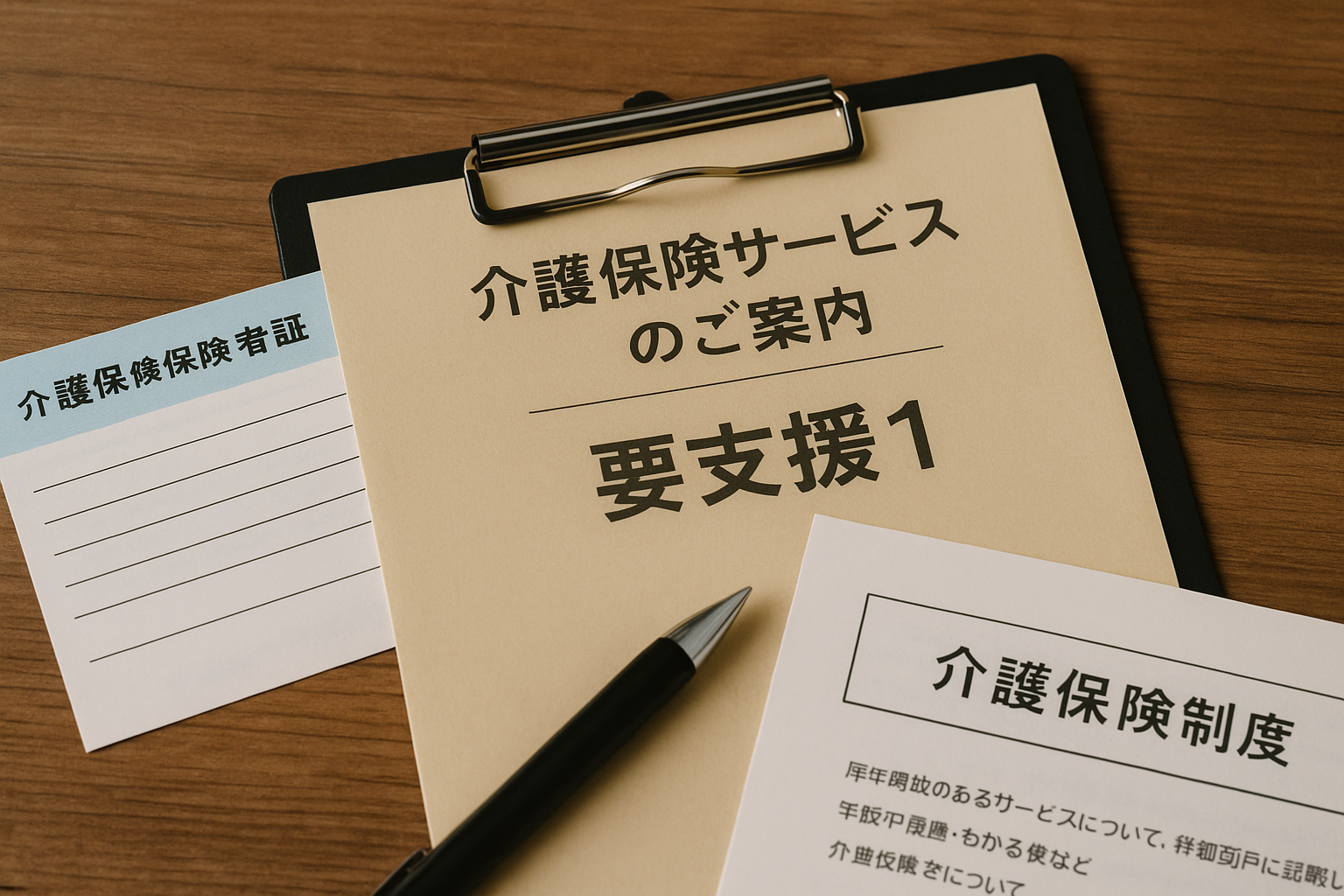「お母さん、要支援1に認定されました」
介護認定の結果を聞いたとき、「これでいろんな支援が受けられるのか」と思っていました。
でも、実際に申請を進めてみると——
「これも対象外」「それには条件があって…」「事業所が少ない」など、
“要支援1”という認定が思っていたよりも“中途半端”であることに気づきました。
この記事では、母が要支援1に認定されてから
実際に申請・利用したサービス、逆に「使えなかったもの」や注意点を、リアルにまとめていきます。
目次
1. そもそも「要支援1」ってどんな状態?
ざっくり言えば、「基本的には自立して生活できるけれど、一部サポートが必要な状態」です。
たとえば:
- 記憶が少しあいまいで声かけが必要
- 家事や買い物が一人だと不安
- 筋力の低下がみられる
ただし、日常生活動作(ADL)はある程度できるとされるため、
「介護」としての支援はかなり限られます。
2. 実際に使えたサービス一覧
僕の母が利用できたのは以下の通り:
- 週1回のデイサービス(介護予防型)
→ 軽運動やレクリエーション中心 - 訪問型サービスA(見守り・会話支援)
→ 15〜30分の見守り訪問。ヘルパーによる家事支援は対象外 - 配食サービス(自治体連携)
→ 一部の市町村で要支援対象の補助あり
正直な感想:「これだけ…?」でした。
3. 申請してみたけど“使えなかった”もの
- 福祉用具レンタル(ベッドなど)
→ 要支援1では原則対象外 - 家事代行・買い物代行
→ 所得制限+本人の同意+ケアマネ判断が必要 - 通院の送迎
→ 医療保険扱いになり、介護保険では非対応
制度上OKでも、実際には“使いにくい”ことが多いと実感しました。
4. ケアマネさんと話すときに大事なこと
要支援の場合、ケアマネージャーの提案内容がほぼすべてになります。
でも、ケアマネさんも「忙しい」「制度が複雑」で、
こちらが希望を明確に伝えないと、適用されないサービスも多いんです。
なので、準備すべきは:
- 何ができなくて困っているか(買い物?料理?歩行?)
- 週何回・どんな時間帯に支援があると助かるか
- 使ってみたいサービス(知ってる限りでもOK)
5. 「要支援」の時期がむしろ重要な理由
「要介護」になる前、要支援の時期こそ“今後を左右する準備期間”です。
この段階でできること:
- 筋力を維持するためのリハビリや体操
- 栄養管理・食事のバランス
- 家族との連携体制を組んでおく
介護予防=将来の負担軽減にもつながります。
まとめ|要支援1こそ“情報戦”です
「まだ介護じゃないから大丈夫」じゃない。
要支援1は、制度とサービスを知らないと“何も使えない”状態にもなりがちです。
この記事が、「まずは何が使えるか調べてみよう」と思うきっかけになれば嬉しいです。